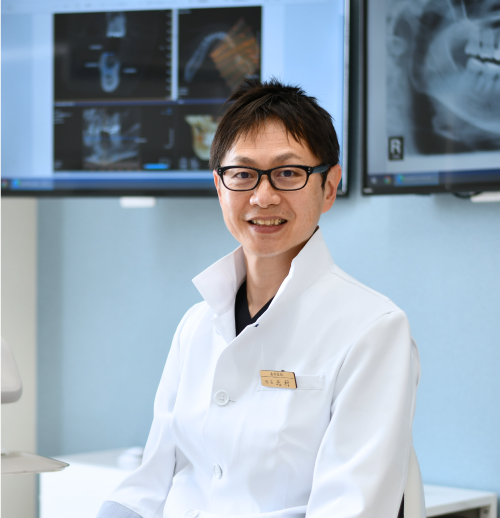「最近なんとなく噛みにくい」「鏡を見ると、歯ぐきが下がってきた気がする」
そんな小さな違和感の背後に、「あごの骨」の変化がひそんでいることがあります。
歯科の専門用語で「骨吸収(こつきゅうしゅう)」と呼ばれるこの現象は、あごの骨が徐々に減っていく(=溶けていく)変化のこと。多くの方にとっては馴染みのない言葉ですが、実はとても身近な問題です。特徴的なのは、痛みや出血といった明確な症状がないまま進行すること。つまり、本人が気づかないうちに骨の量が減り続けているケースが少なくありません。
とくに注意したいのは、歯を失ったあとに治療をせず、そのまま放置しているケースです。歯を支えていた部分の骨は、噛む刺激が加わらなくなると「役割を終えた」と判断され、少しずつ痩せていきます。これが、将来的な入れ歯の不安定さや、インプラント治療の難易度に直結することもあります。
ここでは、「なぜ骨が溶けるのか」「どんな人に起こりやすいのか」そして「どう対処すればよいのか」について、わかりやすく解説しています。歯や骨を長く健康に保つためにも、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
骨が溶ける2つのメカニズム
骨が失われていく背景には、大きく分けて2つのメカニズムが存在します。どちらも初期段階では自覚症状が少ないため、気づいたときにはすでに進行しているケースが少なくありません。
① 歯周病による「炎症性の骨吸収」
歯周病は、歯と歯ぐきのすき間(歯周ポケット)に細菌がたまり、炎症が慢性的に続く病気です。この炎症が長く続くと、やがて炎症が歯を支える骨(歯槽骨)にまで及び、骨が少しずつ溶けていきます。これは身体が炎症反応によって自ら骨を破壊してしまう仕組みで、放置すれば歯のぐらつきや抜け落ちにもつながります。
② 歯を失った後の「非炎症性の骨吸収」
もう一つの原因は、歯を抜いた後に何も処置をせず放置している場合です。歯がなくなると、食事や会話でかかっていた刺激が骨に伝わらなくなり、「使われない骨」となって次第に痩せていきます。このような骨の吸収は炎症がなくても起こり、特に奥歯など目立たない部位では気づかれずに進行してしまうこともあります。
このように、骨が溶ける現象は炎症による破壊と、刺激がないことによる萎縮の2つの方向から進んでいきます。
骨が溶けると起こる深刻な問題
「あごの骨が溶ける」と聞いても、実際にどんな影響があるのかイメージしづらいかもしれません。しかし、骨の吸収が進行すると、見た目や健康、治療の選択肢にまで影響が及ぶ可能性があります。
見た目の変化:輪郭が変わり、老けた印象に
骨が痩せることで、ほおや口元がくぼんだように見えることがあります。とくに歯を失った部分の骨が失われると、支えを失った唇まわりのボリュームが減り、「老けて見える」と感じる方も少なくありません。
治療が難しくなる:入れ歯やインプラントが合わない
骨の量が減ると、インプラント治療を行うのに十分な骨が残っていないこともあります。また、入れ歯も安定しづらくなり、「噛めない」「外れやすい」といったストレスが出てくることも。
このような場合、骨を増やす「骨造成」という治療を行う必要があり、治療期間や費用が増えることもあります。
他の歯にも影響:ドミノ倒しのように悪化することも
骨が失われると、周囲の歯を支える力も弱くなります。その結果、健康だった歯がぐらついてきたり、噛み合わせのバランスが崩れたりといった二次的なトラブルが起きることもあります。
このように、骨の吸収は単なる局所的な問題ではなく、お口全体の機能や見た目、そして治療の可能性にまで関わる深刻な現象です。
大切なのは「早期の対策」
あごの骨が溶ける原因には、歯周病による炎症や、歯を失った部分の放置などがありました。これらに共通するのは、初期の段階での対応が予防や回復の可能性を大きく左右するということです。
歯を失ったら「放置せず」次の選択を
歯を抜けたままにしておくと、骨には咀嚼(そしゃく)による刺激が伝わらなくなり、徐々に痩せていきます。
この変化はゆっくりですが、数ヶ月〜数年の間に骨の厚みや高さが明らかに減ってしまうこともあります。
そうなる前に、入れ歯・ブリッジ・インプラントといった補綴治療を検討し、「噛む力を骨に伝える環境」を整えることが重要です。
特にインプラント治療は骨との結合が前提となるため、骨が十分に残っている段階での検討が理想的です。
骨が足りない場合でも「骨造成」という方法があります
すでに骨の吸収が進んでいる場合でも、治療の選択肢がまったくなくなるわけではありません。
骨造成(こつぞうせい)という治療によって、骨の厚みや高さを再建することが可能です。
ただし、治療期間が長くなったり、手術の難易度が上がることもあるため、やはり「早めの判断」が何よりも大切です。
歯周病は「沈黙の病気」、だからこそ定期的な検診を
歯周病は、自覚症状が出たときにはすでに進行していることが多い病気です。
「歯ぐきが赤い・腫れている」「出血しやすい」などのサインがある場合は、すぐに受診を。
定期検診でのチェック・クリーニングにより、骨の吸収を未然に防ぐことができます。
その「違和感」を放置しないで
「噛みにくい」「歯ぐきが下がってきた」「入れ歯が合わない気がする」
そんな違和感の裏には、あごの骨が静かに吸収・減少しているという見えない変化が潜んでいるかもしれません。
骨は一度失われると自然には再生されにくく、失ったあとで治療の難易度が大きく上がることもあります。だからこそ、「まだ困っていないから大丈夫」と思わず、違和感のある段階での早期受診が、将来の選択肢を広げる大きな鍵になります。
当院では、CTによる3D画像診断を用いて、目に見えない骨の状態をしっかり把握することが可能です。骨の量や質を的確に評価したうえで、患者さん一人ひとりに合った治療法をご提案しています。
気になる症状がある方も、そうでない方も「骨が溶ける前にできること」を、一緒に考えていきましょう。
北村英二 院長について
「歯医者は怖い!」―子どもの頃、私もそう思っていました。説明もなく痛い治療はトラウマでした。だからこそ、北村総合歯科では、患者様の不安に寄り添い、丁寧な説明と痛みの少ない治療を大切にしています。
日本大学松戸歯学部卒業後、様々な歯科医院での経験を経て2021年に開業。インプラント治療はもちろん、虫歯や歯周病、予防歯科まで幅広く対応し、地域の皆様の歯の健康をサポート。「ここに来てよかった!」と思っていただけるよう、笑顔でお待ちしています。お気軽にご相談ください。