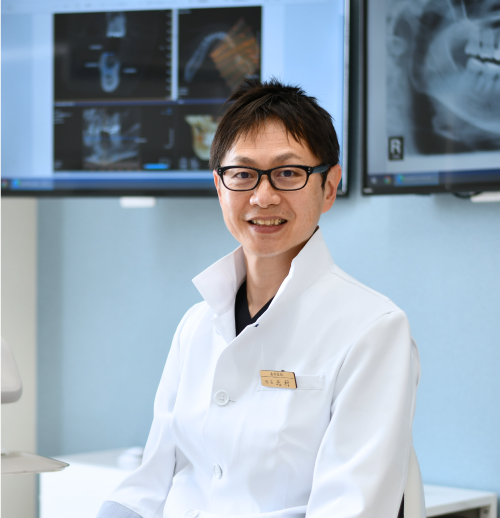「歯並びは遺伝によって決まるもの」
そう思っていませんか?
確かに、歯の大きさや顎の骨格には遺伝的な要素が関わります。
でも、実はそれ以上に大きな影響を与えるのが乳幼児期の生活習慣です。
特に、生後0〜3歳は顎の骨がぐんぐん成長する時期であり、この時期にどのように口を使い、どのような姿勢で過ごしているかが、将来の歯並びに直結します。つまり、歯が生えそろう前から、歯並びを整える「土台づくり」は始まっているのです。
たとえば、
- 哺乳瓶やストローを長く使い続ける
- 口がポカンと開いたままになっている
- 噛む経験が少ない
- 抱っこの姿勢が崩れている
こうした日常の中の小さな習慣が積み重なることで、顎の発達が妨げられ、歯がきれいに並ぶためのスペースが確保できなくなることがあります。
逆に言えば、この乳幼児期に正しい習慣を身につけることができれば、将来的に歯列矯正が不要になる可能性もあるのです。
ここでは、0〜3歳の間に実践できる「歯並びを良くするための習慣」を、わかりやすくご紹介していきます。
今すぐ見直したい!歯並びに影響する生活習慣
日々の育児の中には、気づかないうちに歯並びや顎の発達に影響を与えている習慣がいくつもあります。特別なことをしていなくても、「何となく続けている育児習慣」が、歯列不正のリスクを高めてしまうことも。
ここでは、特に注意したい代表的な習慣を紹介します。
口が開いたままになる癖(=口呼吸)
無意識のうちに口が開いていたり、口で呼吸する癖があると、舌の位置が下がり、上顎を押し広げる力が弱くなってしまいます。
本来、舌は上顎にぴったりついているのが自然な状態であり、そうすることで上顎が横に広がり、歯が並ぶスペースが確保されます。
しかし、口呼吸の癖があると舌が下がり、顎の成長が不十分になり、結果的に歯並びが悪くなる原因になります。また、口が乾きやすくなることで虫歯や歯肉炎などのリスクも高まります。
哺乳瓶・ストローの長期使用
哺乳瓶やストローは便利ですが、口の筋肉の使い方が偏ってしまいます。
特に2歳を過ぎても哺乳瓶を使っていると「乳児の舌の使い方」が残ってしまい、顎の幅が狭くなる原因に。卒乳後はできるだけふつうのコップを使いましょう。
噛む機会が少ない
柔らかい食べ物が中心になると、前歯や奥歯をしっかり使う機会が減ります。
噛むことで顎に刺激が伝わり、骨の成長が促されます。手づかみ食べや歯ごたえのある食材を取り入れることが重要です。
姿勢が崩れやすい抱っこや寝かせ方
縦抱っこ紐を使っているときなどに、首が後ろへ反った姿勢になっていると、口が開いてしまいやすくなります。このような姿勢が続くと、口呼吸の癖がつきやすくなり、顎の発達に影響を与える原因となることがあります。
また、寝ているときにいつも同じ方向を向いていると、頭の形に偏りが生じ、顎の発達や歯並びにも左右差が出てしまうことがあります。
こうした「向き癖」は、赤ちゃんが片側ばかりを向く環境や抱っこの仕方が影響していることも多いため、寝かせる方向をこまめに変えるなどの工夫が大切です。
抱っこ紐の使い方や、寝かせるときの姿勢にひと手間かけるだけでも、将来的な歯並びのリスクを減らすことができます。
体を使った遊びが足りない
寝返り・ハイハイ・雑巾がけなどの動きは、体幹だけでなく、口や舌の発達にも関わる大切な運動です。
歩けるようになるとハイハイを飛ばしてしまう子もいますが、あえて体を低くして動く遊びを取り入れると、全身のバランスが整い、顎の成長にもプラスになります。
これらの習慣を意識して見直すことが、歯並びの良い土台をつくる第一歩になります。
歯並びを育てる0〜3歳の育児習慣7選
ここからは、乳幼児期に実践しておきたい歯並び予防の具体的な習慣をご紹介します。どれも特別なことではなく、日常の中で意識するだけで取り入れられる内容です。小さな積み重ねが、健やかな口腔発達と歯並びの土台をつくります。
卒乳は1〜2歳までに!その後はコップ飲みへ
母乳や哺乳瓶での飲み方は、舌を前後に動かして吸う「乳児の舌の使い方」です。この動きが長く続くと、舌が上顎につかないまま癖づき、顎の成長が妨げられます。
理想は1歳までに卒乳し、遅くとも2歳頃までには完了すること。そして、卒乳後はストローやスパウトではなく、ふつうのコップで飲む練習をすることが大切です。こぼれにくいコップは便利ですが、舌の動きが乳児期のまま残ってしまい、口の機能の発達を妨げる原因になります。
親御さんにとっては少し大変かもしれませんが、顎をしっかり育てるためには「こぼれる経験」も大切です。
正しい抱っこで「口呼吸の癖」を防ぐ

首が後ろに反った状態での抱っこは、口が開いて口呼吸になりやすくなります。特に縦抱っこ紐を使うときは、子どもの首をしっかり大人の体に沿わせ、顎が引ける姿勢を意識しましょう。
首が座っていない時期の縦抱っこは、顎や舌の成長に悪影響を与える可能性があるため避けた方が無難です。また、長時間の使用は避け、使用後には首や背中を優しくマッサージしてほぐしてあげるとよいでしょう。
手づかみ食べをたっぷりと

手で食べ物を持ち、自分で口に運ぶ「手づかみ食べ」は、目・手・口の連動を促し、口周りの筋肉や舌の使い方、噛む力の発達にもつながります。
手が汚れる、食べこぼしが多くなるなど、つい避けたくなるかもしれませんが、発達のためにはとても重要な経験です。
特におすすめなのは、大きめのおにぎり、とうもろこし、骨付き肉、春巻き、バナナなど、手で握ってしっかり口に入れられるサイズの食材です。
野菜や干し芋で「歯固め」トレーニング
前歯や奥歯をしっかり使って噛むことで、歯の周囲の骨が刺激を受けて発達します。離乳食が完了する時期になったら、少しかたいものにチャレンジする「歯固め食材」を意識してみましょう。
たとえば、ゆでたごぼう、干し芋、ブロッコリーの茎、昆布、タコの足、キャベツの芯、鶏のムネ肉やささみなどがおすすめです。
手に持った時に、少し口からはみ出すくらいのサイズにしてあげると、前歯や奥歯を使いやすくなります。
ハイハイ・「雑巾がけ」で体幹を鍛える
歩けるようになっても、ハイハイは終わらせなくて大丈夫です。
ハイハイをはじめ、トンネルくぐりや手押し車などの動きは、体幹や口周りの筋肉、舌のコントロール力を育てるうえで非常に重要です。
特におすすめなのが、雑巾がけのような姿勢で、床に手をついて前進する動きです。この動きは肩・背中・腹筋などの全身を使う運動であり、口を閉じた状態で鼻呼吸を促す姿勢にもつながります。
こうした遊びの積み重ねが、自然と正しい姿勢や呼吸、そして歯並びの土台づくりに役立っていきます。
遊びながら口周りの筋肉を鍛える
歯磨きが始まる前の時期から、口の中に水を含んで動かす「ブクブクうがい」の練習も効果的です。
お風呂で大人が見本を見せながら一緒に練習すると、楽しく取り組めます。
また、「ラッパを吹く」「あっぷっぷ」「にらめっこ」「ストローでふーっと吹く」などの遊びも、口唇や頬、舌の筋肉のトレーニングになります。
向き癖・頭の形が歯並びに影響する?
実は、歯茎の形と頭の形はリンクしていると言われています。
たとえば、赤ちゃんがいつも同じ向きで寝ていて、頭の片側だけが平らになってしまうと、顎の発達や歯列に左右差が出てしまうことがあります。
寝かせる向きをこまめに変えることや、顔が片側にばかり向かないように工夫することで、こうした影響を最小限にすることができます。
歯並びのためにできる専門的なアプローチ
ここまでご紹介してきたように、歯並びや顎の発達は、乳幼児期の生活習慣によって大きく左右されます。
とはいえ、どれだけ気をつけていても、遺伝的な要因や生活環境、成長のスピードによっては歯列不正が起こることもあります。
そんなときに検討したいのが、成長段階に合わせた専門的なサポートです。
歯並びの土台は「口の機能」にあり
歯がきれいに並ぶためには、歯そのものだけでなく、舌・頬・唇など口のまわりの筋肉や呼吸、姿勢のバランスがとても重要です。
たとえば、
- 口呼吸の癖がある
- 舌が上顎につかない
- 姿勢が悪い・猫背になりやすい
- 噛む力が弱い
といった状態が続くと、顎の発達が妨げられ、歯並びの乱れにつながることがあります。
成長期の自然な発達を活かす「筋機能矯正」という選択肢

当院では、こうした問題に対して、マイオブレース治療(筋機能矯正)という選択肢をご用意しています。
これは、舌の位置、呼吸のしかた、姿勢、口周りの筋肉の使い方を整えることで、顎の自然な成長を促し、歯がきれいに並ぶためのスペースを確保していく治療です。
従来のようにスペース確保のために歯を抜いて並べるのではなく、成長期ならではの発育の力を活かして、根本から改善していくことが特徴です。
お子さんがリラックスした環境で取り組めるトレーニング形式のため、痛みや違和感も少なく、歯並びだけでなく全身のバランスや姿勢の改善にもつながると注目されています。
- 将来の矯正をできるだけ避けたい
- 顎の発達が遅れている気がする
- お口ぽかんや口呼吸が気になる
といったお悩みをお持ちの方には、早めのご相談がおすすめです。
「今」できることで、将来の歯並びは変わる
歯並びというと、生えそろってから考えるものと思われがちですが、実際には0〜3歳の間の生活習慣や育て方が大きく影響します。
この時期にどのように口を使い、舌を動かし、体を育てているかによって、顎の成長や歯の並び方に差が出てくるのです。
とはいえ、特別なことをする必要はありません。
今回ご紹介したような日々のちょっとした工夫を取り入れるだけでも、歯並びの土台づくりは十分に可能です。
そしてもし、「口が開いたまま」「舌が下がっている」「噛む力が弱い」など、少しでも気になることがあれば、専門的なアプローチを早めに検討することも大切です。
当院では、歯の状態だけでなく、お子さまの口腔機能や顎の発達、呼吸や姿勢まで含めてトータルにサポートするマイオブレース治療を行っています。
お子さまの歯並びやお口の癖で気になることがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
北村英二 院長について
「歯医者は怖い!」―子どもの頃、私もそう思っていました。説明もなく痛い治療はトラウマでした。だからこそ、北村総合歯科では、患者様の不安に寄り添い、丁寧な説明と痛みの少ない治療を大切にしています。
日本大学松戸歯学部卒業後、様々な歯科医院での経験を経て2021年に開業。インプラント治療はもちろん、虫歯や歯周病、予防歯科まで幅広く対応し、地域の皆様の歯の健康をサポート。「ここに来てよかった!」と思っていただけるよう、笑顔でお待ちしています。お気軽にご相談ください。